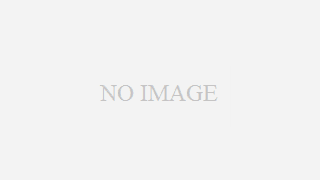 linux
linux let’s encrypt の要らなくなった証明書を削除する方法
let's encrypt の要らなくなった証明書を削除する方法
現在の証明書の確認
sudo certbot certificates
このコマンドで出てきた証明書のいずれを削除したい場合
方法は二つ1
s...
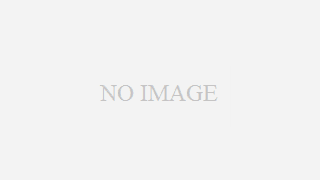 linux
linux 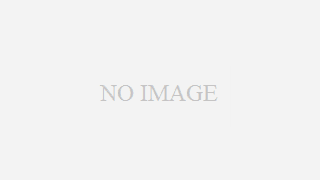 linux
linux 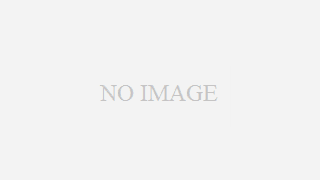 linux
linux 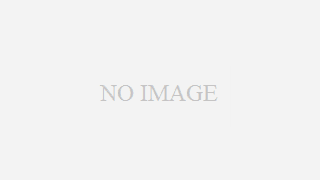 linux
linux 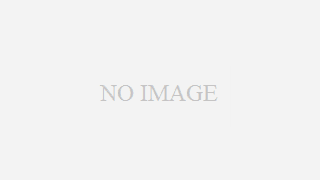 linux
linux 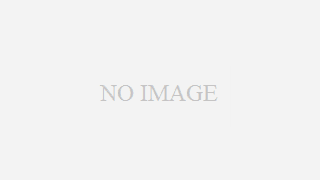 linux
linux